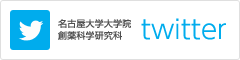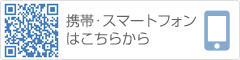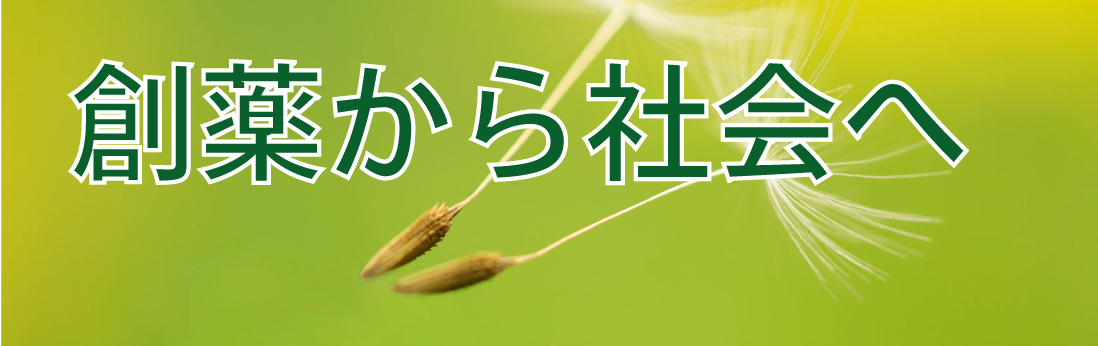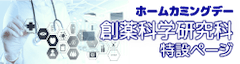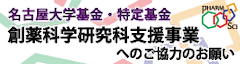創薬科学研究科(細胞生理学研究センター)の藤吉特任教授が記者発表を行いました。
内容を聞けば聞くほどドキドキします。次の記者発表が楽しみになります。
詳細につきましては,名古屋大学ホームページ等ご覧ください。
************************************************************************************
例えば,我々の体の皮膚は,体内の水分が外に放出するのを防いでいますが,完全に外との出入りを遮断されているわけではありません。同様に胃や腸の壁も胃液や腸液が外に出ないようにブロックしていますが,必要なものの吸収や不要なものの排出は行われています。藤吉グループは,細胞と細胞をつなぐところに存在するタイトジャンクション(TJs)と呼ばれるベルト状の細胞間接着構造に含まれる膜タンパク質「クローディン」が,ナトリウムイオンや塩素イオンの出入りなどを制御しており,クローディンは27種類あることや,さらにそれぞれの特徴などを次々と解明してきました(昨年4月に記者発表済)。この解明は,タイトジャンクションの存在が知られてから,15年間,誰も成し遂げられなかった快挙です。
今回は,クローディンの19番について解明しました。
食中毒の原因菌の1つであるウェルシュ菌が作り出す毒素(エンテロトキシン;CPE)は,人や家畜の腸内上皮細胞に結合し傷をつけることで下痢を引き起こすことが知られていますが,その最初の過程で,毒素の一部分(C-CPE)が,クローディンを受容体として結合するときに,どのような複合体構造を形成し,どうやってタイトジャンクション(TJs)のベルト状形態を壊すのかを,名古屋大学と大阪大学の共同研究により解明し,Science誌に発表しました。この構造から,クローディンが掌のような形状をした細胞外部分で,毒素の一部分(C-CPE)を3本の指先で掴むように認識していること,更に,毒素との結合に伴い立体構造が変化するため,ベルト状のタイトジャンクション(TJs)が壊れていく機構も明らかにしました。
これらの成果は,ウェルシュ菌が関わる食中毒メカニズムの解明のみならず,脳などの体のある一部分に,ある薬をピンポイントで吸収させることができるような,新規ドラッグデリバリー法の開発などに繋がることが期待されます。