メンバーMEMBER
教授 山本 芳彦
e-mail : yamamoto.yoshihiko.y9(at)f.mail.nagoya-u.ac.jp
 ORCID Web of Science |
1968年 愛知県生まれ 1991年 名古屋大学工学部 卒業 1996年 名古屋大学 博士(工学) 取得 1996年 名古屋大学 助手 2003年 名古屋大学 助教授 2006年 東京工業大学 准教授 2009年 名古屋大学大学院工学研究科 准教授 2012年 名古屋大学大学院創薬科学研究科 教授 |
准教授 安井 猛
e-mail: yasui.takeshi.k4(at)f.mail.nagoya-u.ac.jp
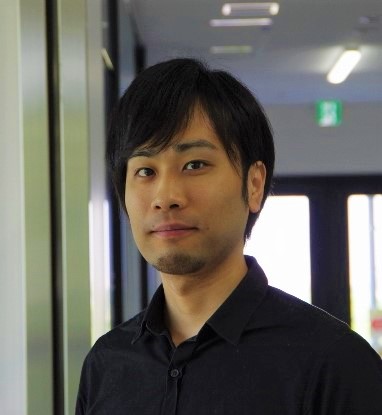 ORCID Web of Science |
・1984年 愛知県生まれ ・2008年 名古屋大学工学部 卒業 ・2010年 スクリプス研究所(Prof. P. S. Baran) 短期留学 ・2013年 名古屋大学 博士(工学) 取得 ・2013年 武田薬品工業株式会社 入社 ・2014-2015年 Tri-Institutional Therapeutics Discovery Institute (NY, USA) 派遣 ・2016年 武田薬品工業株式会社 主任研究員 ・2017年 武田薬品工業株式会社 退職 ・2017年 名古屋大学大学院創薬科学研究科 助教 ・2025年 名古屋大学大学院創薬科学研究科 准教授 |
メールアドレスの (at) には、@ を入れてください。
学生
| D3 | 但野 龍(東京電機大卒)、緩鹿 創太(信州大卒) |
| D1 | 井出 勇人(静岡大卒) |
| M2 | Liu Ning(河北医科大卒)、林 優太朗(山形大卒) |
| M1 | 内田 裕貴 (名古屋大)、平山 大将 (名古屋大)、 藤井 凛人 (名古屋大)、亀村 公平(東京理科大)、 小林 駿斗(芝浦工大)、實末 雄介(徳島大)、 |
| B4 | 片岡 親身、栗栖 あずさ、菱田 草平 |
卒業生の声
山本研で学び、社会人となった卒業生に、学生時代を振り返ってもらいました!これから山本研を目指す後輩たちへのメッセージも述べてもらいましたので、是非ご覧ください。

山本研に入り、思い通りの研究成果がでない中から新しい知見を見出そうとする姿勢が身につきました。未知の有機合成に挑むと、何の反応も進行しない、目的物が生成せずに反応溶液が真っ黒に変色するなど、予想外の結果の連続で良く打ちのめされました。一方で、予想外の結果は新しい研究方針を定めるヒントを含んでおり、それを追求することこそが未知の分野を切り開く鍵であると学びました。
山本研に入って、研究者として生きていくための基礎能力を高めることができた点が良かったと思います。まず、様々な研究テーマを追求する機会を得たことです。山本研は、薬学部や理学部など複数分野の学生で構成されているため研究の自由度が高く、金属触媒、固体触媒、有機分子触媒、フッ素化学、生理活性物質の探索など幅広いテーマに触れられました。現在は半導体製造プロセスの開発という、山本研時代とは異なる研究テーマを進めていますが、この多様な経験が、新たな研究分野にも柔軟に対応できる能力を養いました。また、異なる分野の専門家と協力するスキルや経験も身につき、これは社内外の研究者と開発を進めるうえでも役に立っています。
後輩へのメッセージ:
粘り強く努力し、まだ見ぬ有機合成の世界を切り開いてほしいと思います。その経験が、世界で活躍できる研究者へと成長させてくれるはずです。成功を祈っています。
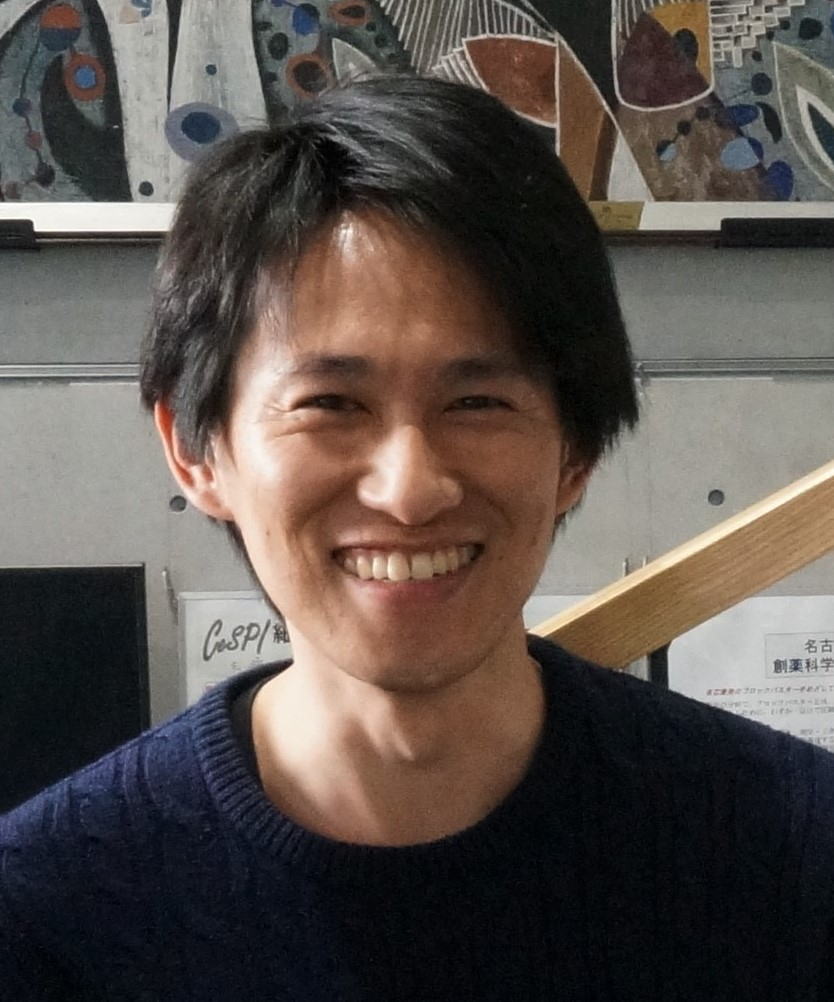
(https://researchmap.jp/takashi-kurohara)
私は、博士前期課程、博士後期課程の延べ5年間在籍しておりました。学部までの化学は教科書の内容をインプットし、試験でアウトプットするというプロセスを取ります。一方で、研究では課題を解決するために、インプットすべき情報を自分で探し、整理して、実験に反映させ、研究を進める、というより実践的な化学が必要です。その活きた化学を、高い水準で身に着けることができました。それも山本教授の手厚いご指導と、研究室メンバーと切磋琢磨できる環境が整っていたためだと思います。
卒業後は分子設計化学分野で培った“有機化学”を武器に、医薬品および食品をターゲットにした化学の応用研究を行っています。山本研で研究できて良かったことは、卒業後1~2年ぐらいの時期は「レベルの高い化学研究に触れることができたこと」と良く感じておりました。社会に出て様々な研究者と交流すると、自分が質の高い有機化学を学んでいたことに気づきました。さらに5年経過した最近では、社会人となった卒業生と顔を合わせることもあり「多様で優秀な人材と出会えたこと」に感謝する機会も増えました。今でも学会などで顔を合わせることがあり、各々の活躍談を聞くことが楽しみです。
後輩へのメッセージ:
他大学からの進学であった私の場合、1年目は研究のスピードとレベルについていくことに必死だったことを良く覚えています。研究生活では上手くいかないことも多々ありますが、それは同時に成長するチャンスでもあります。先生方のご指導を賜れたこと、また、研究室のメンバーと助け合えたことで、辛いことも成長のチャンスに変えることができました。この環境で自分を成長させてみませんか?
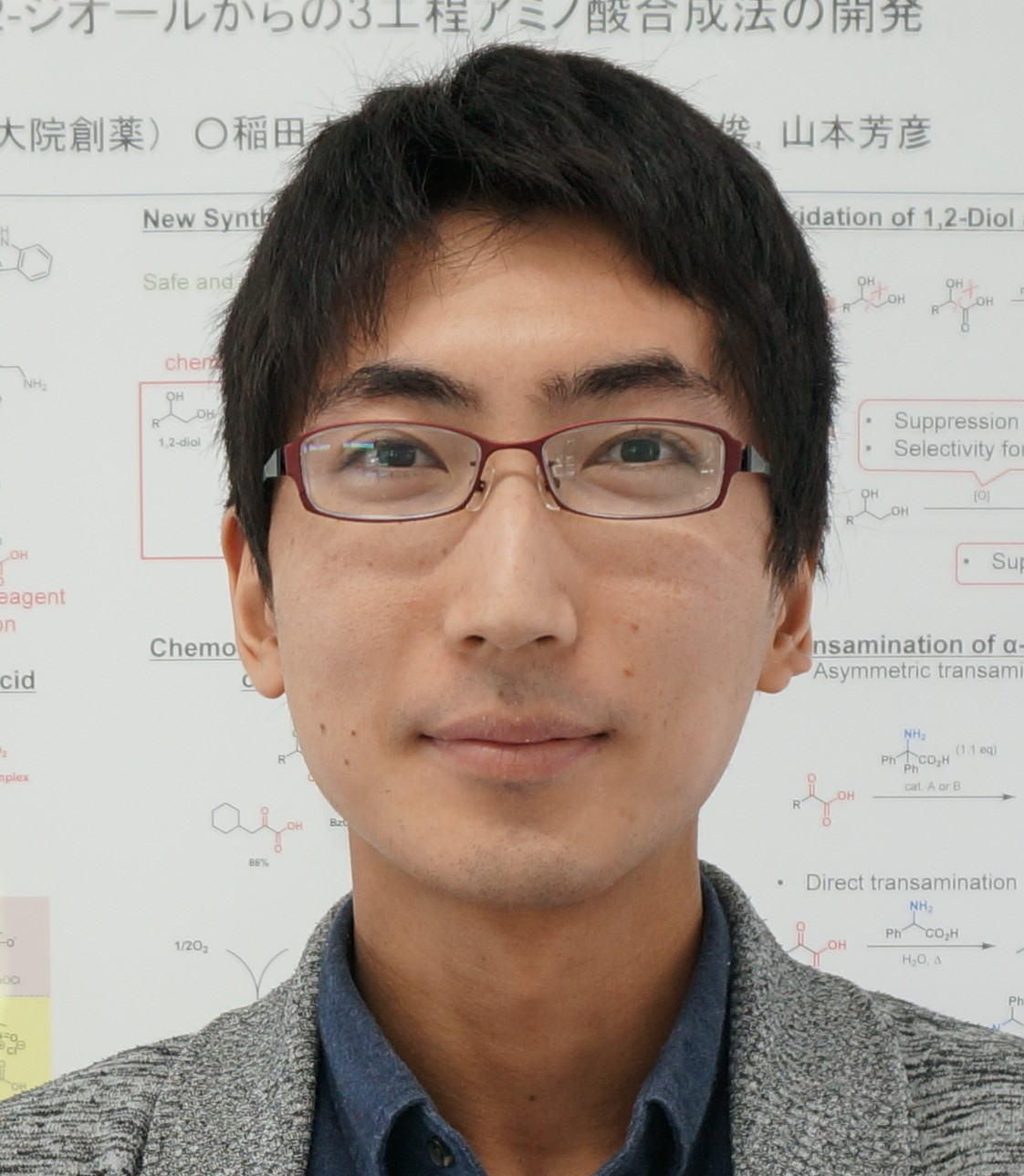 稲田 大輝 (2020
博士卒)
稲田 大輝 (2020
博士卒)
山本研究室でB4からD3までの6年間を過ごし、研究面はもちろんのこと精神的にも大きく成長することができました。指導教員の先生や先輩の熱心な指導の下、実験手技や研究の基礎をB4の1年間でおおいに学びました。その後の5年間は、学んだことを活かして「自身」で研究テーマ・課題を設定し、研究を通して実証していくことで、自身の力で研究を組み立てることができるようになりました。研究報告会や雑誌会では、先生方との多岐にわたる質疑応答を通じて6年間みっちりと鍛えられたことで、強固な理論武装ができるように成長しました。また、指導教員の先生からはプレゼンや文章での表現方法といった研究実績のアウトプットの仕方を学び、今でも資料作成の度に教わったことを活かして仕事をしています。
現在、私は製薬会社の研究者として日々研究に励んでいますが、現在の苦労は何のことはなく、私なら何とかできると確信を持っています。なぜなら山本研での充実した6年間を乗り越え、1つの研究を完遂した事実が今の私に大きな自信を与えているからです。
後輩へのメッセージ:
山本研を志すみなさん、是非山本研で自身の力で研究を組み立てる力を身に着けてください。そして、貴重な在学期間後悔のないよう思う存分研究を楽しんでください。

有機化学の教育が手厚く、B4で配属された当初は院試勉強会で先生から丁寧に教えてもらえたので、有機化学の知識が身につきました。実験・研究の方法についても、入った当初は実験手順が全く分からない状態だったので、基礎の基礎から教えていただきました。特に、スピード感をもって実験を進める方法を学べたと思います。また、当初は人前で話すことがとても苦手だったのですが、研究発表の資料作りや発表の方法を先輩や先生から親身になって教えていただき、ある程度発表に慣れることができました。
自分の研究内容が国際論文としてアクセプトしてもらったときはかなりの達成感がありました。自分の名前が載った論文が世に出ていることは今でも私の誇りです。学会発表の機会も何度か与えられ、学外での発表の経験を積めた点もよかったと思っています。また、日常生活の面では、研究室がある創薬棟は比較的新しい建物なので実験室がきれいです。一階に売店があり、外に出なくてもご飯やおやつを買えるところもいいところです。研究室旅行で夜まで飲み会をしたり、会議室で餃子を作って食べたりと、研究の息抜きになるイベントを開催できたのもいい思い出です。
後輩へのメッセージ:
B4の4月に山本研への配属が決まり、気が付いたときには修士課程を修了していました。振り返ると全力で実験をし、全力で息抜きのイベントを楽しんだ3年間でした。有機化学の研究に関して右も左もわからない状態でも、研究内容については先生にサポートしていただけるのでその点は心配ないです。一度創薬棟に見学に来てもらい、どんな楽しいイベントを開催しようか、考えてから入ってくるといいと思います。
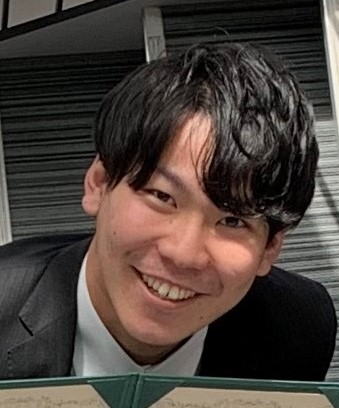 黒柳 英佑 (2022
修士卒)
黒柳 英佑 (2022
修士卒)
創薬科学研究科は創薬をメインテーマとする学科であるため、有機化学、生物化学など多様な研究に触れられます。山本研では、知識や研究方法はもちろんのこと、研究成果の魅せ方についても学ぶことができました。研究では創薬に貢献し得る化合物を生み出そうと多方面からアプローチし、最終的に論文という形で成果を発表できた経験は、大きな自信となりました。成果が求められる社会では、自らの仕事の価値の魅せ方はとても重要であるため、山本研でご指導いただいた日々が自分の土台になっていると強く感じます。一方で、研究生活ではうまくいかないことの方が多かったので、みんなで昼食を食べたりコンビニに行ったりと日常的な交流がとても支えになりました。他大学からの進学も多いので、その分新しい出会いがあり、いろいろな人と交流ができることも魅力の一つです。
後輩へのメッセージ:
研究に邁進したい人、これまでの自分を変えたい人、山本研究室をオススメします。3年生までの生活と大きく変わるので最初は抵抗があるかもしれません。しかし、研究を通して自分の考えが成果に繋がっていく喜びやその過程での自分の変化に驚くことになると思います。成長できる環境が山本研究室には揃っていますので、一歩踏み出してみてください。

僕は、有機化学、その中でも遷移金属錯体を触媒として用いる新しい反応の開発に興味があり、山本研の門を叩きました。配属された当時、研究に関して右も左も分かっていませんでしたが、山本研での研究活動を通して、研究遂行能力、論理的思考力、プレゼンテーション能力、英語力など研究者に必要な能力を磨くことができたと思っています。厳しく大変であったと同時にとても充実していて、結果として、三つの新しい反応を世界に先駆けて開発し、それらの反応機構の解明にも注力することができました。現在は、山本研で培った能力を活かして、企業で研究を続けています。
後輩へのメッセージ:
社会に出て年齢を重ねるごとに、身体的にも環境的にも、一つの物事に熱中することが難しくなります。一方、大学院では、研究に没頭できる恵まれた環境が整っています。とりわけ、山本研はとても教育熱心な研究室であり、研究に没頭しつつ、研究者として大きく成長することができると思います。有機化学が大好きな人、生涯かけて研究をやりたい人、成長することに貪欲で向上心の高い人、ぜひ山本研を目指してみてください。
山田 啓士(2025 博士卒)
僕は、B4の時の研究室配属において、山本研究室へと配属されることになりました。第一希望の研究室ではなかったため、初めは少し残念に思う気持ちもありましたが、先生方の熱い指導と有機化学の奥深さに魅了され、B4の終わり頃には博士後期課程に進学することを心に決めていました。6年間の研究生活では、思うように成果が出ない時期もありましたが、最終的には、自分にしか達成できないユニークな研究成果を世に発表できたことを誇りに思うとともに、揺るぎない自信を与えてくれたと感じています。また、研究報告会や雑誌会では、先生方だけではなく、先輩や同期、後輩たちとの熱いディスカッションを行ったことで、臆することなく自身の意見を述べる度胸を身につけることができたと感じています。山本研で得た知識や経験を十分に活かして、これから社会に貢献していきたいです。
後輩へのメッセージ:
山本研究室は非常にレベルの高い研究を行っていながら、教育にも非常に熱心であり、研究能力はもちろんのこと、プレゼン技術や資料作成能力などの社会で必要な能力も同時に鍛えられる環境が整っています。有機化学の研究者を志す学生には、山本研究室を強く勧めます。また、先生方は非常に器が大きく、研究に関する意見は何でも受け止めてくださるため、臆することなく自分の意見やアイデアをぶつけましょう。そのような経験ができる環境も多くはないと思います。これらの恵まれた環境を十分に活かして、素晴らしい研究成果を出すことを期待しています。
バナースペース
分子設計化学
〒464-8601
名古屋市千種区不老町
TEL 052-747-6800, 6801
FAX 052-747-6800, 6801